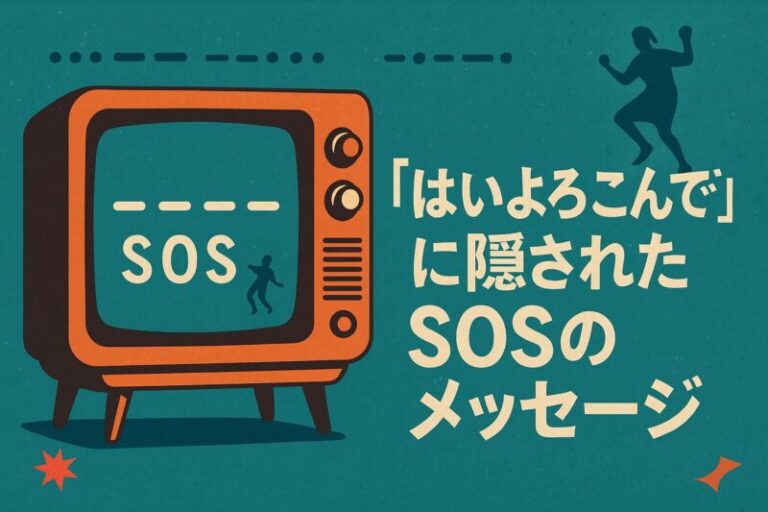2024年、SNSで爆発的な話題となった「はいよろこんで」。耳に残るメロディとギリギリダンスで注目を集める一方、その中に潜むモールス信号「トントントンツーツーツートントントン」の意味に多くの人が興味を持っています。
実はこのリズム、国際的な遭難信号「SOS」を表しており、こっちのけんとさん自身の実体験から生まれたメッセージが込められているのです。心が限界に近づいたときに発する無言のサインとして、このメロディがどれほどの影響力を持っているか、ご存知でしょうか?
この記事では、「はいよろこんで」に込められたモールス信号の意味と、その背景にあるこっちのけんとの想い、そしてSNSで共鳴する人々の声までを徹底解説します。
「はいよろこんで」に込められたモールス信号「トントントンツーツーツートントントン」の意味とは?
2024年、TikTokを中心に注目を集めた楽曲「はいよろこんで」には、リズムの中にモールス信号が含まれているという話題が広まりました。
このモールス信号「トントントン ツーツーツー トントントン」は、国際的な遭難信号である「SOS」を意味しています。
一見すると明るくリズミカルなこの曲ですが、その中には深刻なメッセージが込められており、多くの人がその意味に心を動かされました。
「はいよろこんで」の歌詞には「鳴らせ君の3から6マス」という表現があります。
この「3から6マス」とは、心電図における心拍の正常範囲を示しており、身体は正常でも心が限界に近づいている状態を象徴しています。
つまり、精神的に追い込まれる前に、自分の状態に気づき助けを求めてほしいというメッセージが込められているのです。
モールス信号が歌詞の中に登場するのはサビの前です。
しかし、ミュージックビデオの映像では最後の「トン」、つまり「・」が一つ欠けている演出がされています。
これは「SOS」が「SO」で止まってしまったように見え、ギリギリで助けを求めることすらできない状態を表しているとも解釈されています。
このように「はいよろこんで」は、楽曲としての魅力だけでなく、現代社会における心の健康や助けを求めることの大切さを伝える作品でもあります。
リスナーの中には、モールス信号の意味を知ってから曲の印象が大きく変わったという声も多く見られます。
音楽を通じて、見えにくい心のサインに気づくことの重要性が改めて認識されるきっかけになっています。
なぜモールス信号を使ったのか?こっちのけんとの実体験と制作秘話
「はいよろこんで」にモールス信号が使用された理由には、こっちのけんと本人の実体験が深く関係しています。
本人によると、精神的に追い詰められていた時期があり、助けを求めたい気持ちがありながらも、それを直接言うことができなかったと語っています。
その葛藤の中で、言葉ではなく別の形で自分の思いを伝えたいという気持ちから、モールス信号という表現にたどり着いたそうです。
制作時期は、前作「死ぬな!」の反響を受けて様々な仕事が舞い込んできた頃でした。
こっちのけんとは、与えられた仕事に「はいよろこんで」と応じ続け、自分の限界に気づかないまま無理を重ねていたといいます。
その結果、周囲と連絡が取れなくなるほど心身のバランスを崩し、立ち止まらざるを得なくなったと語られています。
そのような状況下で、日々メモしていた言葉や感情をもとに生まれたのが「はいよろこんで」です。
特に、サビ直前に差し込まれるモールス信号は、自身の「助けて」という心の叫びを、暗号のように作品に忍ばせる手段だったと述べています。
それは、直接的な表現ではないからこそ、気づいた人にだけ伝わる形で、本人の本心がそこに残されていると感じられます。
こっちのけんとの語りからは、単なる演出ではなく、実体験から生まれたリアルな感情が楽曲に込められていることが伝わってきます。
聴く人がその背景を知ることで、より深くこの曲に共感し、受け取るメッセージにも変化が生まれるでしょう。
モールス信号を選んだのは、伝えたいけれど伝えられなかった感情を、音楽という形で届けるための必然だったのかもしれません。
ミュージックビデオの演出が物語る“途中で途切れたSOS”
「はいよろこんで」のミュージックビデオには、楽曲の内容に込められたメッセージを視覚的に表現する細かな演出が施されています。
特に注目されているのが、サビ前に流れるモールス信号「SOS」の最後の「・(トン)」が欠けている描写です。
映像では「・・・ーーー・・」となっており、本来の「SOS」とは微妙に異なって見えることが話題となっています。
この「・」がひとつ足りない表現は、意図的に行われていると考えられています。
それは、助けを求めたい気持ちがあるのに、最後の一歩がどうしても踏み出せない、という心情を象徴しているようです。
まるで「SO」で止まってしまったかのような表現は、精神的に限界を迎えた人が声を出すことすらできない状態を映し出しています。
また、ミュージックビデオ全体の演出にも注目が集まっています。
昭和レトロな雰囲気や、キャラクターたちのかわいらしい動きが印象的な一方で、主人公の表情にはどこか寂しさや疲れを感じさせる描写が含まれています。
明るい音楽と対照的に、映像の中には違和感や孤独感が巧みに織り交ぜられているのです。
このように、ミュージックビデオの演出は、曲そのもののメッセージを補完し、視聴者により深く受け止めてもらうための工夫が施されています。
特に、「最後のトンが欠けている」ことに気づいた人たちは、その違和感を通して、表面に見えない苦しみや声なき叫びに目を向けるようになります。
音だけでは伝えきれない部分を、映像が担うことで、「はいよろこんで」はより多層的な意味を持つ作品となっています。
「はいよろこんで」がTikTokでバズった理由
「はいよろこんで」がSNS、特にTikTokを中心に爆発的な広がりを見せた背景には、いくつかの要素が組み合わさっています。
その中でも最も大きな要因のひとつが、耳に残るメロディとリズム感、そして「ギリギリダンス」と呼ばれるキャッチーな振付です。
このダンスは曲のサビに合わせて手を交差させる動きが特徴で、多くのユーザーが動画を投稿し始めたことで一気に拡散されました。
さらに、TikTokでは「#はいよろこんで」や「#ギリギリダンス」といったハッシュタグが急速に浸透しました。
ユーザーが自分のダンス動画を投稿することで、他の人も挑戦したくなる流れが生まれ、自然と再生数が増加していったのです。
こうしたユーザー参加型の仕組みは、TikTokのアルゴリズムとも相性がよく、投稿のバズりやすさにもつながっています。
また、サビ直前に挿入されているモールス信号の部分が印象に残りやすく、視覚と聴覚の両方でインパクトを与える演出となっています。
「何か意味があるのでは?」と感じたユーザーがその真意を調べ始め、自然と楽曲の背景やアーティストの意図にたどり着く構造になっていました。
このように、コンテンツの中に謎や意図を感じさせる要素があることで、リスナーの興味が深まり、拡散が加速したと言えます。
結果として、YouTubeやInstagram Reelsでも関連動画が大量にアップされ、TikTokでの総再生回数は数億回に到達するほどのムーブメントになりました。
単なる「踊ってみた」ではなく、楽曲の内容や演出に触れながら共有されていることが、他の流行曲との違いを生み出している要因です。
「はいよろこんで」がバズった理由は、音楽性、演出、SNSの仕組み、そして聴く人自身の共感を呼ぶテーマが、うまく重なり合った結果といえるでしょう。
モールス信号が再評価されている理由
モールス信号は19世紀に通信手段として発明され、長年にわたって無線通信や海上での遭難信号として使われてきました。
現在では実用的な通信手段として使われることは少なくなりましたが、近年は新たな文脈で再評価される機会が増えています。
その背景には、音楽やアート、教育といった分野での創造的な活用が広がっていることが関係しています。
特に音楽の分野では、リズムや音の強弱を利用してモールス信号を取り入れる試みが行われています。
こっちのけんとの「はいよろこんで」におけるモールス信号の使用もその一例であり、楽曲に隠されたメッセージとしてリスナーの関心を引きました。
ほかにも、海外アーティストが曲のイントロやドラムパターンにモールス信号を取り入れる事例もあり、音楽表現の一手段としての活用が進んでいます。
教育現場でも、モールス信号はプログラミング教育の一環として取り上げられるようになっています。
信号の規則性や変換の仕組みは、論理的思考や暗号理解の学習に役立つとされ、小学生から高校生まで幅広い世代で学習教材として活用されています。
また、スマートフォンのアプリやデバイスの機能を使って、視覚や振動でモールス信号を学べるツールも登場しています。
アートの分野では、光や音を使ったインスタレーションでモールス信号を用いる表現も登場しています。
こうした作品は、観客がその場で意味を読み解く体験を通して、メッセージを深く受け取る仕掛けになっています。
感情やテーマを暗号的に伝える手段として、モールス信号の持つシンプルさと奥深さが注目されているのです。
このように、かつての通信技術であるモールス信号は、現代においても創造的な表現や学びのツールとして生まれ変わりつつあります。
「はいよろこんで」のような楽曲をきっかけに、その存在を初めて知った人や興味を持った人も少なくないでしょう。
モールス信号は、言葉では伝えきれない感情や意味を、音やリズムに変えて届ける力を持った表現手段として、再び注目を集めています。
ファンの声に見る、「はいよろこんで」が与える影響
「はいよろこんで」は、音楽としての完成度だけでなく、その裏にあるメッセージ性が多くの人の共感を呼んでいます。
特に、モールス信号による「SOS」に込められた意味に気づいたリスナーたちからは、さまざまな感想や思いがSNSに投稿されています。
それらの声を通して、この曲が人々の心に与えている影響が浮かび上がります。
まず多く見られたのが、「明るい曲なのに涙が出た」という感想です。
リズムやメロディは軽快で親しみやすいものの、背景を知ることで楽曲の印象が大きく変わったと話す人が少なくありません。
表面的な楽しさと、その裏にある深いメッセージとのギャップが、聴く人の感情に強く響いているようです。
また、「助けを求めることは悪いことじゃないと気づいた」という声も多く見られました。
モールス信号という暗号を通じて気づきを得たリスナーたちは、自分の経験や心の内をSNS上で共有するようになっています。
特に「#心の健康」「#はいよろこんで」といったハッシュタグを通して、共感の輪が広がっている様子がうかがえます。
さらに、「自分も限界だったときにこの曲に救われた」と語る人もいます。
音楽を通じて自分の状態に気づいたり、誰かに話してみようと思えたという体験談が投稿されており、曲がきっかけとなって行動が変わった例も報告されています。
楽曲が単なる娯楽にとどまらず、リスナーの内面に働きかけていることがよくわかります。
このように、「はいよろこんで」は、聴く人に寄り添い、励まし、時には行動を促す力を持っています。
ファンの声に耳を傾けることで、この曲が音楽以上の価値を持って受け入れられていることが明確になります。
それは、現代のリスナーがただ楽しむだけでなく、自分の心と向き合うためのきっかけを音楽に求めていることを示しているのかもしれません。
「はいよろこんで」モールス信号に込められたメッセージのまとめ
「はいよろこんで」は、表面的には楽しく踊れるポップソングでありながら、その内側には深い意味が込められた作品です。
特に、曲中に挿入されたモールス信号「SOS」は、こっちのけんと自身の実体験をもとにした助けを求めるサインでした。
この楽曲は、直接的な言葉ではなく、音やリズムを通して、心の苦しみや限界にある人の気持ちを伝えようとする表現として受け止められています。
ミュージックビデオで「SOS」の最後の「・」が欠けていたことは、声を上げたくても上げられない人の存在を象徴していました。
その表現が、視聴者に「自分や他人の心のサインに気づくことの大切さ」を伝えています。
明るい曲調とのギャップが、そのメッセージ性をさらに印象的にしているとも言えるでしょう。
また、この曲をきっかけに、助けを求めることは恥ずかしいことではないという認識が広まりつつあります。
SNSを通じて多くの人が自身の体験や思いを共有し、共感の輪が広がっているのはその証拠です。
音楽が単なる娯楽を超え、社会的なテーマに光を当てる力を持っていることが、この曲によって改めて示されました。
こっちのけんとの「はいよろこんで」は、現代に生きる人々が感じている孤独や葛藤を代弁する作品です。
モールス信号を通じて伝えられたその思いは、多くのリスナーに届き、深い共感と反響を生み出しました。
これからも、このような音楽が心の支えとなるよう、多くの人に届いていくことを願っています。